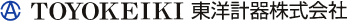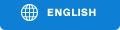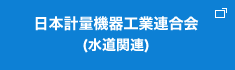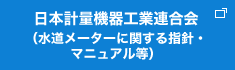2021年10月18日 日本の蚕糸業を支えた「はかる道具」
夏から秋へと季節が変わり、肌寒い日も多くなってきました。衣替えされた方も多いのではないでしょうか。
衣服には様々な素材が使用されており、その中の一つに、絹(シルク)があります。絹の原材料である生糸を生産する蚕糸業(蚕種業・養蚕業・製糸業の総称)は、昭和初期まで長野県内でも盛んに行われていました。
今回は、日本の蚕糸業で活躍していた「はかる道具」をご紹介いたします。
蚕種業
蚕種(蚕の卵)の製造は、雄と雌を判別することから始まります。雌雄の鑑別は、蚕の繭を切り開いて中の蛹を取り出し、鑑別士が行っていました。繭を切開する手間や専門の知識が必要となる、大変な作業だったようです。
そこで、より簡単に効率良く雌雄の鑑別ができるよう考案されたのが、「雌雄鑑別器」です。
蚕の雌はある一定の基準より重い、という特性を利用し、はかりを使用して雌雄の鑑別を行います。雌雄鑑別器は、様々なタイプのものが考案されました。

こちらは、「中塚式雌雄鑑別器」です。繭を落とす滑り台が付いています。

こちらは、「田崎式雌雄鑑別器」です。お皿に繭を乗せ、回転させながら使用します。
従来の雌雄鑑別器より、より速く、より多くの蚕の雌雄を判別することができます。

蚕種の孵化も、大変重要な作業でした。卵からうまく孵化させるためには、育ちやすい環境作りが必要となります。
そこで使用されたのが、こちらの「蚕当計」です。この蚕当計で温室内の温度管理を行っていました。
養蚕業
桑の栽培や蚕の飼育、繭の生産は、養蚕農家によって担われていました。

こちらは、「桑枡」です。桑の葉の量を量るのに使用されていました。
蚕は、桑の葉を食べて育ちます。絹織物1反分(着物約1着分、約1kg)の蚕を育てるのに、約98kgの桑の葉が必要といわれています。

養蚕農家が生産した繭は、製糸業者へ引き渡されます。こちらの丸型の「繭枡」は、取引をするときに、繭の量を量るために使用されていました。
製糸業
明治時代になり、1872年(明治5年)に富岡製糸場(世界遺産)が操業されると、富岡製糸場を模範として全国へ技術が伝播され、製糸業の発展に伴い蚕糸業はますます盛んになったといわれています。1909年(明治42年)には、日本は世界一の生糸輸出国となりました。
輸出用の生糸は、品質調査のため様々な検査を受けていました。

こちらの「検位衡」は、糸の綿密度(太さ・重さ)を測定するのに使用されていました。

「水分検査機」です。生糸の水分含有量を求めるための機械で、生糸の乾燥前後の重さを比較することで無水量を測定していました。
丸みを帯びた形がダルマに似ていることから、通称「ダルマ」とも呼ばれています。

こちらの「再繰機」は、生糸をボビンに巻き取る機械で、巻き取った際の生糸の切れた回数の検査をします。
「ふわり」と呼ばれる木製の器具が付いており、このふわりに生糸を掛けて回して使用していました。

生糸の節検査を行うための「セリプレーン機」です。専用の検査板に生糸を巻き取り、標準見本の生糸と目視で比較していました。
節の少ない生糸が、より品質の良い生糸です。

生糸の強度や伸びを測定するための機械、「スーター式セリグラフ」です。生糸を引っ張り切断することで検査していました。

出荷用に整えられた生糸を「括(かつ)」といい、こちらは括を製造するための「括造り器」です。
世界遺産富岡製糸場で、当時富岡製糸を指導したフランス人、ブリューナー製作の貴重なものです。

括には、生糸の品質が書かれた札と、生産した製糸工場の商標が付けられていました。
商標には、植物や動物など多種多彩に工夫された芸術性の高いデザイン画が印刷されており、輸出された生糸に付けられた商標は当時、海外の愛好家に大変人気があったようです。

生糸に限らず、一つの商品を出荷するために数多くの「はかる道具」が使用され、私達の身近に溢れています。東洋計量史資料館ホームページでは、他にも様々な「はかる道具」をご紹介していますので、ぜひご覧ください。